手紙が消えたあと、人類は何を遺跡として残すのだろう
手紙が消えたあと、人類は何を遺跡として残すのだろう
デンマークの国営郵便企業 PostNord が、2025年12月30日をもって、ほぼすべての郵便物配達業務を終了するというニュースを知ったとき、最初に浮かんだ感情は驚きではなかった。
「やはり、そうなるよね」という、静かな納得だった。
メール、チャット、電子署名。
日常のやり取りはすでに紙を必要としなくなっている。
郵便が非効率なインフラになるのは、ある意味で自然な流れだ。
けれど、少し時間が経ってから、別の違和感が胸に残った。
これは単なる郵便制度の終了ではない。
人類が“言葉を残す方法”を、また一段階手放した瞬間なのではないか、と。
⸻
古代文明が発見されるとき、そこには必ず物質として残った言葉がある。
石に刻まれた命令、粘土板の記録、羊皮紙の日記、誰かに宛てた手紙。
そこには政治だけでなく、恐れや願い、愛情や愚痴といった、人間の生の文面が残っている。
では、もし現代文明が何らかの形で途切れたあと、未来の現生人類や、あるいは別の知的生命体が地球を発掘したらどうなるだろう。
彼らは、私たちの文明をどこで読み取るのだろうか。
クラウドに保存されたテキスト。
暗号化されたストレージ。
電力を前提としたサーバー群。
それらは、人間がいなくなった瞬間に、ほぼすべて沈黙する。
データ文明は、驚くほど大量の情報を生みながら、同時に驚くほど脆い。
考えてみれば、これは皮肉な話だ。
私たちは史上もっとも多くの言葉を残している文明でありながら、史上もっとも未来に読まれにくい文明でもある。
⸻
ふと、空想が膨らむ。
もしかすると、私たちが「謎の古代文明」「突然消えた高度文明」と呼んでいる存在も、実は同じだったのではないか。
彼らは高度すぎて、石に刻む必要がなかった。
情報をエネルギーや有機体、あるいは高度な媒体に保存していた。
けれど文明が途切れた瞬間、その記録媒体ごと消えてしまった。
結果として、後世には「何も残らなかった文明」として扱われる。
存在していたのに、読めない。
だから神話になる。
もし未来に、壊れたデータセンターの残骸だけが見つかったら、私たちも同じ扱いを受けるのかもしれない。
巨大な冷却装置と意味不明な配線だけを残した、声の聞こえない文明として。
⸻
これは北欧だけの話ではない。
日本でも、同じ変化はすでに始まっている。
年賀状の枚数は年々減り、挨拶はSNSやメッセージアプリに置き換わった。
「出さなくても問題にならない」という空気が広がり、手書きの挨拶は、静かに日常から姿を消しつつある。
けれど、日本は少し不思議な場所だとも思う。
手紙やカードは完全には消えていない。
日常からは後退したが、祝祭の中には残っている。
特別なとき、特別な感情を伝えるときだけ、紙が呼び戻される。
結婚、別れ、葬儀、記念日。
あるいは、未来の自分に宛てた手紙や、タイムカプセルという形で。
それなら、いっそ発想を逆にしてもいいのではないかと思う。
手紙を義務や慣習として残すのではなく、祝祭として再設計する。
たとえば、バレンタインのように、恋愛に限らない「言葉を贈る日」。
家族へ、友人へ、あるいは十年後の自分へ。
チョコレートの代わりに、言葉を渡す。
クリスマスカードを贈るでもいい。
年に一度だけ、あえて非効率を楽しむ週間があってもいい。
切手を貼り、ポストに投函するという行為を、体験として祝う。
若い世代には新鮮で、年配の世代には懐かしい、時間の交差点として。
⸻
デジタルと紙は、対立する必要はない。
デジタルは速く、紙は残る。
デジタルは共有でき、紙は痕跡を持つ。
文明の記録を、どちらか一方に賭ける必要はないはずだ。
もし未来の誰かが、瓦礫の中から一通の手紙を見つけたとき、そこに書いてあるのが、
「今日は寒いですね」
「元気にしていますか」
そんな何気ない言葉だったら。
その文明は、きっとこう判断される。
ここには、ちゃんと人間が生きていたと。
郵便が終わる国があってもいい。
デジタル化が進むのも自然だ。
それでも、言葉が物として残る祝祭だけは、手放さずにいてほしいです。
それは未来へのメッセージであり、私たち自身が人間である証明でもなれたらいいですね。



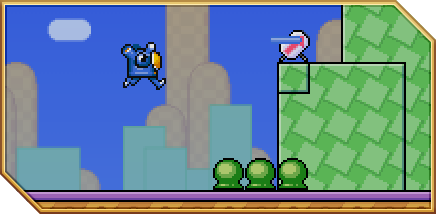
 執筆者
執筆者




 テーマ
テーマ アーカイブ
アーカイブ